 お知らせ
お知らせ あなたの命を守る「マイナ救急」
令和7年10月頃から当組合でも「マイナ救急」実証事業がスタートします。
「マイナ救急」とは、「マイナ保険証」を活用して過去の受診歴や薬剤情報などを閲覧し、皆さんをより円滑に医療機関へ搬送する取り組みのことです。
あなたの命を守るため、「マイナ保険証」を携行しましょう。
 お知らせ
お知らせ  お知らせ
お知らせ 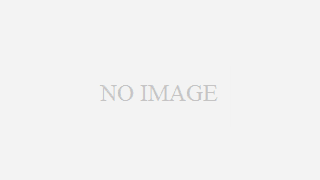 救急関係
救急関係 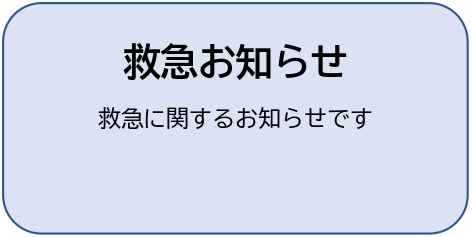 お知らせ
お知らせ 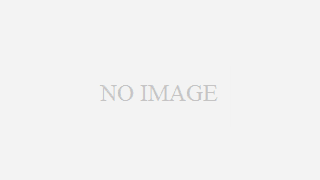 救急関係
救急関係 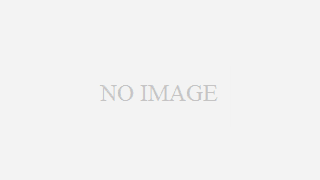 救急関係
救急関係  救急関係
救急関係 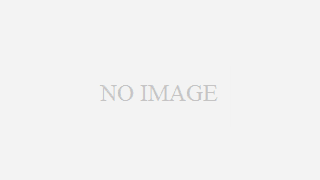 救急関係
救急関係  救急関係
救急関係 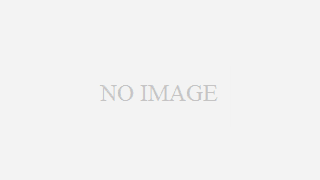 救急関係
救急関係 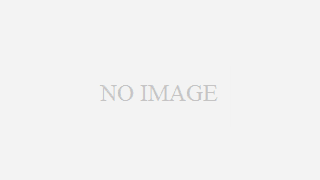 救急関係
救急関係 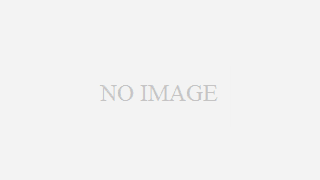 救急関係
救急関係 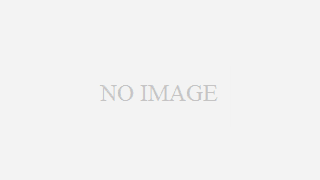 救急関係
救急関係 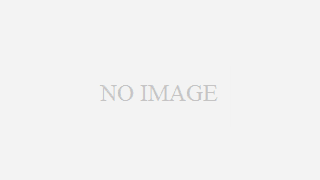 救急関係
救急関係 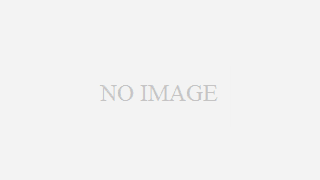 救急関係
救急関係 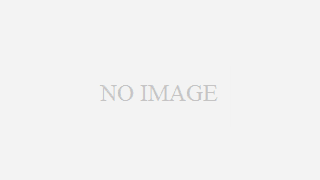 救急関係
救急関係 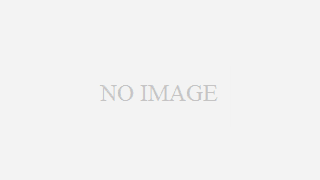 救急関係
救急関係 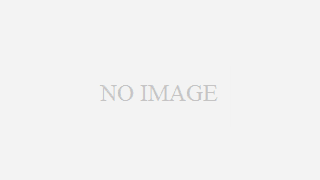 救急関係
救急関係 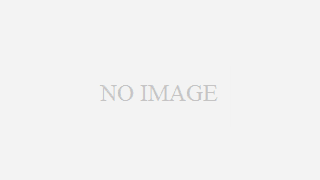 救急関係
救急関係 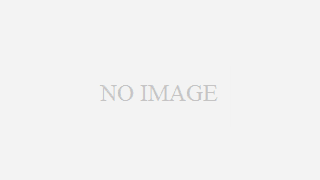 救急関係
救急関係